- 投稿日:2025年06月25日 10時13分
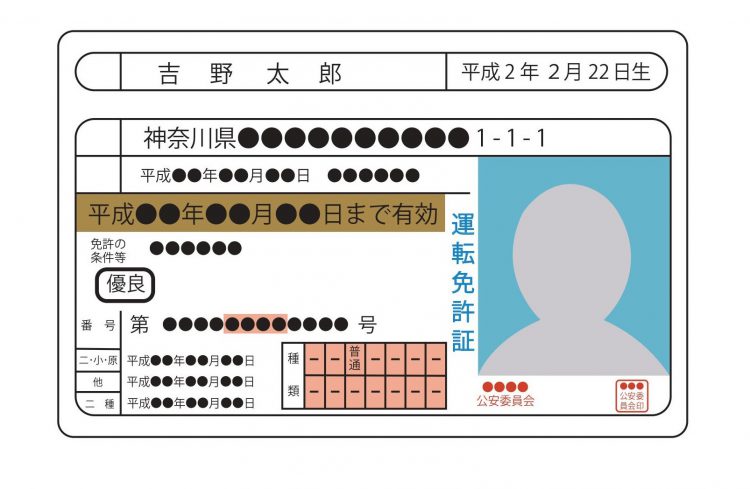
運転免許制度が平成29年(2017年)3月12日に一部改正され、自動車運転免許が少し複雑になりました。
今回の免許制度の改正は貨物自動車による交通事故の削減と、若者の雇用促進のためで、普通自動車・中型自動車・大型自動車の他に新しく「 準中型自動車 」が新設されました。
どのページも分かりにくい!!といった方、必見☆現在の運転免許について、どこよりも見やすくわかりやすく解説していこうと思います。自分が現在、どの免許の区分に当てはまるのか再確認することで、どのトラックなら運転できるか明確に分かりますね!運転できるトラックによって選ぶ仕事内容も変わってくると思うので、是非この機会に確認してみてください~(*^_^*)
Contents
道路交通法の改正
社会的背景を元に度々法改正されながら現在の免許制度に至っています。
平成19年(2007年)6月以前は、普通免許と大型免許だけでした。平成19年6月に中型免許が追加され、今回の改正で準中型免許が追加となります。
また、免許区分が追加されるたびに、普通免許で運転可能な車両の総重量・最大積載量が変更になっています。
準中型運転免許は満18歳から取得することができ、車輌総重量7.5トンまでの自動車・トラックを運転することができます。詳しくは下記より紹介していきますので、すでに運転免許証をお持ちの方も、これから取得予定の方もこの機会に確認してみてください♪

R07 いすゞ フォワード ウイング車 高年式・低走行!増トン★62ワイド・ハイルーフ・リアエアサス | |
| 詳細を見る |

R07 いすゞ フォワード ウイング車 【入庫点検中】高年式・低走行!増トン★62ワイド・ハイルーフ・リアエアサス | |
| 詳細を見る |

R03 いすゞ フォワード 保冷・冷凍ウイング 【入庫点検中】高年式!増トンワイド★全面断熱入!リアエアサス・格納ゲート | |
| 詳細を見る |
自動車免許の取得について
自動車の免許の取得は満18歳の誕生日を迎えなければ取得することが出来ませんが、教習所は普通車の場合、18歳の誕生日の2カ月前から入校することが出来ます。ただ、仮免許の試験を受けられるのは18歳の誕生日からです。
ちなみにバイクですが、普通二輪は16歳の誕生日から、大型二輪は18歳の誕生日から取得が可能です。バイクは小型であれば16歳から免許を取得することが出来ます。
普通自動車よりも大きい、大型免許・中型免許は18歳では取得することができません。理由は、運転初心者が中型・大型クラスを運転するのは危険すぎるということです。
◆中型免許は普通自動車免許を取得してから2年以上経過していて、20歳以上から取得できます。
条件は、仮免許を取得して過去3カ月以内に5日以上の路上運転をした方です。
◆大型免許は「普通第一種免許」「中型第一種免許」「大型特殊第一種免許」のいずれかの免許を取得していて、その期間が通算3年以上であること。(免許の効力が停止されていた期間は除く)
上記に記載があるように、中型免許・大型免許を取得するには、普通自動車免許を持っていることが義務付けられていますので、初めから中型免許や大型免許に挑戦することはできません。まずは普通自動車で運転をマスターしましょう!!
【免許の取得ができる年齢表】
| 免許の種類 | 年齢 | 取得条件 |
| 普通免許 | 18歳以上 | なし |
| 準中型免許 | 18歳以上 | なし |
| 中型免許 | 20歳以上 | 普通免許または大型特殊免許のどちらかを取得し、少なくとも2年以上経過していること |
| 大型免許 | 21歳以上 | 普通免許または大型特殊免許のどちらかを取得し、少なくとも3年以上経過していること |
準中型が新設された理由
平成19年(2007年)の法改正で中型免許が新設されるとともに、普通免許で運転可能な車両の総重量・最大積載量が大きく引き下げられました。
| 普通免許の取得日 | 車両総重量 | 最大積載量 |
| ~平成19年6月 (中型8t限定) |
8トン未満 | 5トン未満 |
| 平成19年6月~平成29年3月 (準中型5t限定) |
5トン未満 | 3トン未満 |
小型トラックでも車種によって冷蔵装備やパワーデートなどの架装状況により、車両総重量約5トンを超えたり、最大積載量3トンを超えてしまうというのが現状です。
かつては普通免許(中型8t限定)で18歳以上で運転できた車両も、総重量5トン以上のトラックを運転する際は「中型免許」が必要となり、取得の年齢制限が20歳以上で、運転免許を取得してから2年以上経過しているという条件があり、若手のドライバーが運送系の仕事を始めるのに大きな障害となっていました。
新設された準中型免許は、それらの問題を改善するように考えられていて、18歳以上から取得が可能になり、車両総重量7.5トン未満と最大積載量4.5トン未満になっています。そのため、より幅広く車種を運転することが出来るようになりました。
いわゆる中型トラックは、車両総重量が7.5トン以上8トン未満の車両が多数を占めており、準中型免許に対応した車両はあまり存在せず、運転するには中型免許が必要となっています。このことからも準中型免許はあえて小型トラックに絞った改正で、サイズが大きくなる中型トラックは20歳以上で経験を積んだドライバーの運転が望ましいという捉え方ができます。
【運転免許の早見表】
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 定員 |
| 普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
| 準中型免許(5t限定) ※旧普通免許 |
5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 |
| 準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 |
| 中型免許(8t限定) ※旧旧普通免許 |
8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 |
| 中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 |
| 大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
※旧普通免許:平成19年6月~平成29年3月に取得した普通免許
※旧旧普通免許:平成19年6月よりも前に取得した普通免許
準中型運転免許について詳しく解説
普通免許と中型免許の間に新しく作られた、車輌総重量7.5トン未満の自動車を運転することができる免許です。平成29年3月12日から、「道路交通法の一部を改正する法律」(改正法)が施行されました。
準中型運転免許は、今までの普通運転免許証と、中型運転免許証の間に新しく作られました。
運転できる自動車は、車輌総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満までです。
普通の一般的な乗用車から小型(2tトラック)クラスのトラックなら運転することができます。また、今まではこのクラスを運転する場合、20歳以上で普通免許等を2年以上もっていることが必要だったんですが、今後は満18歳以上であれば、それ以前の運転経験を問わず運転免許を取得することができます。
免許の更新について
免許を取得する際は規定の年齢以上であることが決まっていますが、年齢の上限はありません。そのため、その気になれば50歳、60歳、70歳を過ぎても自動車学校に通うことが出来ます。免許取得の際には色覚検査・視力検査が行われるので、そこで問題なければ免許を手に入れることが出来ます。若い頃は必要ないかな?と思っていた人でも、年齢を重ねて経済的・時間的に余裕が出てきて、免許をとってみようかな~なんて思う人も少なくないようです。
★70歳以上は「高齢者講習」がある!
最近、増えていますよね・・・高齢者の方がブレーキとアクセルを踏み間違えて起こしてしまう大事故・・・。高齢者の方だけってわけじゃないと思いますが、やはり年齢を重ねると共に、判断力や注意力が衰えていくので注意して運転しなければなりません。
少しでも危険を回避するために、70歳以上は更新前に特別な教習が義務付けられています。講習の対象になるのは、免許証の更新を70歳以上で行う方です。
講習で行われるのは、
- 講義
- 運転適性診断・夜間視力・動体視力検査など
- 実車運転と運転指導
高齢者講習は、講義が1時間、検査が1時間で計2時間となかなか長い拘束時間になります。
そして、高齢者講習を無事終えることが出来なかった場合、教官から免許の返納を進められることがあります。実際、高齢者の事故は増加していますし、その被害に遭う確率も高くなっています。本人に自覚がなくても、運動能力や視力・聴力などは悪くなっていきます。また、地域によっては車がないと生活が不便になってしまうというのも問題の1つです。
自分ではなかなか判断できなかったりするので、周りにいる家族が声をかけ、免許の返納を促せるといいのかもしれないです!
★免許更新の費用・料金
運転免許の更新に必要な費用は、おもに手数料です!
更新手数料は全国一律で同じ金額ですが、講習手数料は免許の区分によって違いがあります。また各都道府県によって、講習手数料に少し違いがあるので、更新する際は各自で確認することをおすすめします。
【手数料一覧】
更新の手数料は全国一律で同じ金額です。70歳未満の方が免許を更新する時に支払う手数料をまとめるとしたの表のようになります。
| 更新手数料 | 講習手数料 | 合計 | |
| 優良運転者 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 |
| 一般運転者 | 2,500円 | 800円 | 3,000円 |
| 違反運転者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 |
| 初回更新者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 |
優良運転者(ゴールド免許保持者)
➡免許を取得して5年以上経っている方で、その5年間、無事故無違反が条件になる
優良運転者の更新にかかる費用。
一般運転者(ブルー免許保持者)
➡免許を取得して5年以上経過している方で、その5年間に軽い違反1回のみの運転者が対象。
※ちなみに軽い違反は、違反点数が3点以下の違反のことです。
違反運転者(ブルー免許保持者)
➡運転免許書を取得して5年以上が経過している方で、その5年間に軽い違反が2回以上、
または違反点数が4点以上の違反を起こした運転者が対象。
初回更新者
➡免許を取得して5年未満で、運転免許取得後に初めて更新する方!
軽い違反が1回以下のドライバーが対象。
(更新する前の免許証の色がグリーンの方が初回更新者です。)
●70歳以上の高齢者の方が更新にかかる費用
◆70歳以上75歳未満
更新手数料:2,500円 + 講習手数料:5,800円 = 8,300円
◆75歳以上
更新手数料:2,500円 + 講習予備検査費650円 + 講習手数料:5,350円 = 8,500円
まとめ
免許制度は社会的背景を元に改正されており普通免許といっても運転できる車両も取得時期によって異なります。免許制度と運送業界は切っても切り離せない存在ではあるものの、免許制度に準拠したトラックの製造や、運送業界のトラックのニーズになかなかマッチしづらい状況はありそうだと感じました。
また、運転免許には有効期限があり、決められた期限内に免許の更新をする必要があります。更新の期限が近づくと、お知らせがハガキで送られてきますが忘れてしまい、免許の更新を忘れてしまう人もいるようです。期限内に更新を行わないと、運転免許は失効となってしまうことになります。6カ月以内なら学科・技能試験を受けずに再取得することが出来ますが、そうならないように気を付けてください。









